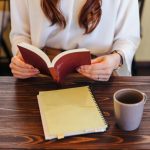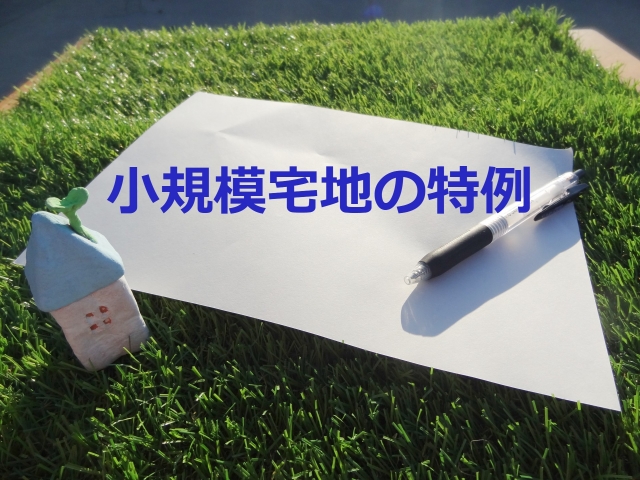
大切な財産を守りながら、税負担を抑えられるかもしれない制度のお話です。まずは使える条件を確認しましょう。

佐藤 智春先生
みらいえ相続 相続専門税理士
専門分野:相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

金(かね)つぐ
資金運用の天才。相続専門の佐藤税理士の相続への熱意と、困っている人々を助けたいという想いから現れた相続勇者。相続の様々な側面を分かりやすく説明し、人々の不安を和らげていく相続勇者。

「前回の相続税とは?にもあった通り、相続税にはいろいろな控除や特例があるみたいだけど、『小規模宅地等の特例』というのを聞いたことがある。これはどんな制度?」

「いい質問ですね!『小規模宅地等の特例』は、相続税を大幅に軽減できる非常に重要な特例です。特に自宅や事業用の土地を相続する場合に使える制度なので、多くの人にとって役立つ内容です。今日はこれについて詳しくお話ししますね。」
小規模宅地等の特例とは?

「まず、小規模宅地等の特例とは何なのか、簡単に教えて。」

「この特例は、被相続人が所有していた宅地(例えば自宅や事業用の土地)について、一定の条件を満たすと相続税評価額を大幅に減額できる制度です。」
(1) 特例の概要
- 相続税評価額が最大で80%減額されます。
- 特例が適用されることで、相続税の大幅な軽減が可能になります。
(2) なぜこの特例があるのか?
- 自宅や事業用の土地は、大きな金額で評価されることが多いため、相続税の負担が非常に重くなるケースがあります。
- この特例によって、税金の負担を軽減し、相続人が自宅に住み続けたり、事業を継続しやすくしたりする目的があります。

「土地の評価額が下がると、それだけ相続税の負担が軽くなるのか。助かる人が多そう!」

「その通りです。この特例は多くの家庭で利用されている重要な制度です。」
特例の対象となる宅地

「どんな土地がこの特例の対象になる?」

「対象になるのは、主に次の3つの種類の土地です。それぞれ条件があるので注意してくださいね。」
(1) 自宅(特定居住用宅地等)
- 被相続人が亡くなるまで住んでいた自宅の土地。
- 減額率:80%
- 適用上限:330㎡まで。
- 主な条件:この特例を受けるための主な条件は、相続する人によって異なります。
1. 配偶者が相続する場合
・被相続人の自宅に引き続き住み続ける必要はありません。
・最も優先的に特例の適用が受けられます。
2. 同居していた親族が相続する場合
・相続税の申告期限まで、その自宅に引き続き住み続ける必要があります。
3. 「家なき子」が相続する場合(被相続人と別居していた親族)
「家なき子」とは、被相続人と別居していた親族で、以下の条件をすべて満たす人を指します。
・被相続人に配偶者や同居していた親族がいないこと。
・相続開始前3年以内に、自分、配偶者、3親等内の親族、または自分と特別の関係にある法人が所有する家屋に住んでいなかったこと。
・相続した宅地を、相続税の申告期限まで所有していること。
(2) 事業用宅地等
- 被相続人が生前に事業をしていた土地(例えば飲食店や工場の敷地)。
- 減額率:80%
- 適用上限:400㎡まで。
- 主な条件:
- 相続人が事業を引き継いで継続すること。
(3) 貸付事業用宅地等
- 被相続人が賃貸物件として活用していた土地。
- 減額率:50%
- 適用上限:200㎡まで。
- 主な条件:
- 賃貸事業を相続人が引き継ぐこと。
- 事業の継続が確認できること。

「自宅だけでなく、事業や貸付の土地も対象で、それぞれ条件が違うんだ。」

「そうです。土地の種類ごとに条件が異なるので、相続前にしっかり確認することが大切です。」
小規模宅地等の特例を使うための条件

「この特例を使うための具体的な条件を教えて。」

「特例を使うためには、土地の種類ごとにさまざまな条件があります。下記以外のも複数条件がありますが、主な条件をまとめました。」
(1) 配偶者が相続する場合
- 配偶者が相続する場合、特例の条件は最も緩やかで、引き続きその土地を利用しなくても適用されます。
(2) 子どもや親族が相続する場合
- 主に、次の条件を満たす必要があります。
- 居住用宅地:相続人が被相続人と同居しており、相続後も引き続き住み続けること。
- 事業用宅地:相続人が事業を引き継ぎ、継続すること。
(3) 適用を受けるための手続き
- 相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に申請する必要があります。
- 申請時には、土地の利用状況や相続人の居住・事業の継続状況を証明する書類が必要です。

「申告期限内に申請しないと特例が受けられないんだ。それは気をつけないと!」

「その通りです。期限を過ぎてしまうと、この大きな特例が使えなくなってしまうので、注意が必要です。また、上記以外にも複数条件がありますので安易に判断はできません。専門家に相談しましょう。」
特例の具体例

「具体的にどれくらい相続税が減額されるのか、イメージが湧きにくいです。」

「では、具体例を挙げてみますね。」
ケース1:居住用宅地
- 土地の評価額:5,000万円
- 特例適用後の評価額:5,000万円 × (100 - 80%) = 1,000万円
→ 4,000万円分の評価額が減額されます!
ケース2:事業用宅地
- 土地の評価額:3,000万円
- 特例適用後の評価額:3,000万円 × (100 - 80%) = 600万円
→ 2,400万円分の評価額が減額されます!

「たった1つの特例で、これだけ評価額が減るなんてすごい!」

「そうなんです。この特例を使うかどうかで、相続税の額が大きく変わりますよ。」
注意点とよくある質問
(1) 特例が使えない場合もある
- 相続人が相続後、申告期限までに土地を売却したり、賃貸に出した場合は特例が取り消されることがあります。
- 被相続人がその土地を生前に使用していなかった場合も、特例は適用されません。
(2) 配偶者以外の親族には制約が多い
- 子どもや親族が相続する場合、居住や事業の継続が求められるため、注意が必要です。
(3) 専門家のサポートを活用
- 特例の適用には条件が多いため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
- 小規模宅地等の特例とは:自宅や事業用の土地の評価額を最大50~80%減額できる制度。
- 対象となる土地:
- 居住用宅地:評価額が80%減額される(上限330㎡)。
- 事業用宅地:評価額が80%減額される(上限400㎡)。
- 貸付事業用宅地:評価額が50%減額される(上限200㎡)。
- 注意点:適用には条件がある。また、申告期限を守ることが重要。

「高い相続税を払わないといけないのかと不安だったけど、この特例があれば安心できる場面も多いんだ。」

「はい、正しく理解して早めに準備すれば、大切な土地を守りながら税負担も抑えられますよ。」
次回も相続について学びます。お楽しみに!
もし小規模宅地等の特例を利用できれば、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。但し、適用条件が多く申告手続きも必要なため、専門家への相談をおすすめします。