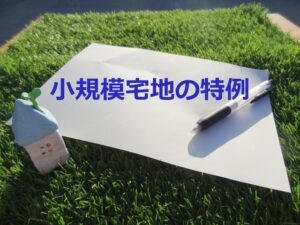相続税の仕組みを知り、わが家に合った対策をすることで納税負担が減らせるかもしれません。まずは相続税の基本について学びましょう。

佐藤 智春先生
みらいえ相続 相続専門税理士
専門分野:相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

金(かね)つぐ
資金運用の天才。相続専門の佐藤税理士の相続への熱意と、困っている人々を助けたいという想いから現れた相続勇者。相続の様々な側面を分かりやすく説明し、人々の不安を和らげていく相続勇者。

「相続に税金がかかるって聞いたけど、具体的にどんな場合に相続税が発生する?」

「相続税は、亡くなった方の財産の総額が一定の基礎控除額を超えた場合に課税される税金です。ただし、基礎控除や特例があるため、すべてのケースで相続税が発生するわけではありません。今日は、相続税の仕組みや計算方法、控除のポイントについて詳しくお話ししますね。」
相続税の基本

「相続税ってそもそもどんな税金?」

「相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際にかかる国税です。遺産を引き継ぐ際に課税されることで、財産の一部が国に納められます。」
(1) 相続税が発生する条件
相続税が発生するかどうかは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えているかどうかで決まります。
- 基礎控除額の計算式:
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)
- 例1:相続人が配偶者1人と子ども2人(計3人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
→ 遺産の総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。 - 例2:相続人が配偶者1人と子ども1人(計2人)の場合
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
→ 遺産の総額が4,200万円以下なら相続税はかかりません。
(2) 相続財産の範囲
相続税の課税対象となる財産には、次のようなものがあります。
- 課税対象の財産:
- 不動産(自宅、土地など)
- 預貯金
- 株式や投資信託
- 生命保険の死亡保険金(一部が非課税)
- 車や貴金属、骨董品などの動産
- 課税対象外の財産:
- 死亡保険金の非課税枠(後述)
- 公共財団などへの寄付金
- 仏壇や墓地などの非課税財産

「なるほど、財産全てが課税対象ではないのか。でも、基礎控除額を超えた分に対して課税される仕組みなんだ。」

「その通りです。課税の対象になる財産とならない財産をしっかり区別することが大切です。」
相続税の計算方法

「具体的には、相続税はどうやって計算する?」

「相続税の計算は少し複雑ですが、次の手順で計算します。」
(1) 計算手順
- 遺産総額の算出
- まず、被相続人が残したすべての財産(課税対象)を合計します。
- 負債(借金やローン)や葬儀費用は控除されます。
- 課税遺産総額の算出
- 遺産総額から、基礎控除額を引いた金額が課税遺産総額になります。
- 法定相続分に応じた課税額を計算
- 課税遺産総額を、法定相続分で分けた金額に基づいて税率を適用し、相続人ごとの税額を計算します。
- 税率表(2025年現在):
| 課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
| ~1,000万円 | 10% | 0円 |
| ~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| ~5,000万円 | 20% | 200万円 |
| ~1億円 | 30% | 700万円 |
| ~2億円 | 40% | 1,700万円 |
| ~3億円 | 45% | 2,700万円 |
| ~6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
- 各相続人の税額を合計
- 計算された税額を合計し、全体の相続税を算出します。
(2) 計算例
- ケース:
- 遺産総額:1億円
- 相続人:配偶者1人、子ども2人(計3人)
- 基礎控除額:4,800万円
- 課税遺産総額:1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
- 相続税の総額の計算(ここが相続税の計算で難しいポイント!):
- 課税遺産を法定相続分で按分
配偶者:5200万円×1/2 =2600万円
子① :5200万円×1/2×1/2 =1300万円
子② :5200万円×1/2×1/2 =1300万円 - 各人に対する相続税を税率表に基づいて算出
配偶者:2600万円×15%-50万円=340万円
子① :1300万円×15%-50万円=145万円
子② :1300万円×15%-50万円=145万円
→合計 配偶者:340万円+子①145万円+子②145万円=630万円 - 実際に受けとった金額の割合に応じて各人の納付すべき相続税額の計算
【実際に受け取った金額】
配偶者:6000万円
子① :2000万円
子② :2000万円 - 【納付すべき相続税額】
配偶者:630万円×6000万円÷1億円=378万円
子① :630万円×2000万円÷1億円=126万円
子② :630万円×2000万円÷1億円=126万円
- 課税遺産を法定相続分で按分

「具体例で計算すると、かなり現実味があるね。税率が高くなると負担も大きいんだ。」

「そうなんです。ただし、控除や特例を活用すれば、税額を大きく減らせる可能性があります。」
- 各種控除の適用
控除の制度は様々ありますが、今回は配偶者の税額軽減を適用します。配偶者には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という制度があり、法定相続分または1億6,000万円までは非課税となります。
→ このケースでは、配偶者の相続額378万円は配偶者控除の範囲内
→ よって、配偶者の税額はゼロ円
最終的な相続税額
配偶者:0円
子ども:126万円 × 2人 = 252万円→ 相続税の合計:252万円
相続税を軽減する方法
(1) 配偶者の税額軽減
- 概要:配偶者が相続する財産には、非常に大きな控除が適用されます。
- 配偶者控除の適用範囲:
- 1億6,000万円まで非課税、または
- 法定相続分までの全額非課税
- 活用例:夫が亡くなり、配偶者がほぼすべての財産を相続する場合、相続税が発生しないケースが多い。
- 配偶者控除の適用範囲:
(2) 小規模宅地等の特例 *次回詳しくご説明します
- 概要:被相続人が住んでいた土地や事業用の土地について、相続税評価額を最大80%減額できる特例です。
- 条件:
- 亡くなった方が住んでいた家に同居していた親族が相続する場合など。
- 特例の対象となる土地の上限面積が決まっています(330㎡など)。
(3) 生命保険の非課税枠
- 概要:生命保険金には、法定相続人の人数に応じた非課税枠があります。
- 非課税枠:500万円 × 法定相続人の人数
- 例:法定相続人が3人の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税。

「特例や控除を使えると、かなり税金を減らせそう!」

「そうですね。これらの制度を活用するかどうかで、最終的な税額が大きく変わることもあります。しかし、相続税の税額軽減や特例が使えるかどうか、またどの特例が最も有利になるかを判断するためには、相続税の専門家に相談することをお勧めします。」
相続税の申告と納税の注意点

「相続税の申告や納税には、何か注意すべきことがある?」

「相続税は申告期限や納税方法に注意する必要があります。」
(1) 申告期限
- 相続開始から10か月以内に申告が必要です。
- 期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるため、早めの準備が必要です。
(2) 納税方法
- 原則:現金一括納付
- 特例:
- 延納:分割払いが可能。ただし、担保の提供が必要です。
- 物納:不動産などを納税に充てる方法。ただし、条件が厳しいため事前の相談が必要です。
まとめ
- 相続税の基礎:遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課税される。
- 控除や特例:
- 配偶者控除、小規模宅地の特例、生命保険の非課税枠などを活用することで、税額を軽減可能。
- 申告期限:相続開始から10か月以内に申告・納税を忘れずに!

「相続税って難しそうだけど、仕組みを知れば対策できることも多いんだ。」

「はい、早めに知って準備すれば、納税の負担を大きく減らすことも可能ですよ。」
次回も相続について学びます。お楽しみに!
「わが家に相続税はかかる?」そんな疑問は将来に備えて解決しておきましょう。何事も早めが肝心ですよ。